こんにちは、カポです。
私が訪れてみたい場所に、新潟の彌彦神社(いやひこじんじゃ)があります。
ここでは、毎年、日本鶏品評会や長鳴鶏の鳴き合わせが、行われています。
当日は、愛鶏家の方々が、唐丸(とおまる)・声良(こえよし)・東天紅(とうてんこう)などを持ち寄り、200羽ほどが出品展示され、美しい姿や鳴き声を競い合います。
秋の菊まつりでは、近隣の道路は渋滞するほど人が訪れるそうですが、
こちらのイベントでは人混みになることもなく、ゆっくり見れそうです。
特に、おすすめは長鳴鶏の鳴き合わせで、必死に鳴く鶏の姿が、とっても可愛いんですよ!
そこで、「長鳴鶏の鳴き合わせって何?日本三大長鳴鶏について調べてみた!」ということで
ご紹介させていただきます。
日本三大長鳴鶏とは
日本には、三大長鳴鶏という鶏がいます。
その名の通り、長い間、鳴いているという意味です。
東天紅(とうてんこう)は、高知原産の鶏で名前の由来は、江戸時代の人が鳴き声を「トーテンコー」と呼んでいたことからついたとか。
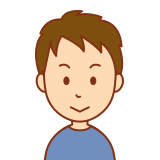
へぇー
当時は、「東天紅」のほかに「東天光」という漢字もあったそうです。
「東天光」には、東の天空が光に包まれてくる頃に、雄鶏が鳴くからという意味があったそうです。
現在の東天紅には、東の空が紅く(明るく)なったころに、雄鶏が鳴く所からつけられました。
昭和11年に天然記念物に指定されています。
東天紅
声良鶏(こえよしどり)は、秋田原産の鶏で、体重は3.5Kg~5Kgもある大型の鶏です。
鳴き声は「ゴッゴゴーオーオー」例えるなら、バイクの音に聞こえる鳴き声です。
声良鶏鳴き声
現在は、北東北で多く飼育され、飼育方法や繁殖、血統種の保存活動などが行われています。
声良鶏は、昭和12年に国の天然記念物に指定されています。
声良鶏
唐丸(とうまる)は、新潟原産の鶏です。
歴史的にはオランダや中国から輸入された大型の鶏に、越後の鶏などを交配して作られた品種だと言われています。
オスの体重は、4Kg前後 メスは3Kg前後
昭和14年に天然記念物に指定されました。
唐丸
日本には、日本鶏という固有種17種が天然記念物に指定されています。
長鳴鶏の鳴き合わせ会とは
毎年5月になると、新潟の彌彦神社では長鳴鶏(ながなきとり)の鳴き合わせが行われています。
簡単に言うと、どの鶏が一番長く鳴くのかを競うものです。
舞台は高い台の上、奥から2羽ずつ連れてこられた鶏は、台に置かれると、ここぞとばかりに鳴き始めるのです!
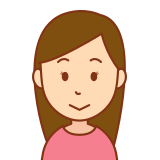
どうして鳴けるのかしら?
実は、仕掛けがあって鶏は順番が回ってくるまで、暗い場所で待機していて、
出番が来ると、突然明るい場所に出されるので“朝が来た”と錯覚して、鳴き始めるのだそうです。
- 制限時間5分
- 舞台に出てから3分以内に鳴かないと退場
- 鳴き声は、5秒以上でカウント
- 5秒以内はノーカウント
- 記録は3回のうちで、一番長く鳴いたもの
- 係員がストップウォッチで計測
- 鶏の鳴き始めと鳴き終わりの計測は係員任せ
係員によって、カウントに誤差がありそうな気もしますが、特に触れることなく進んでいきます。
また、レースに支障をきたすような、奥から聞こえる待機組の長鳴きは、かなり気になりますが放置されたまま進みます。
長く鳴いた鶏には、拍手が送られ、勢いに乗った鶏は、さらに気合が入ります!
個人的主観です(笑)
どのくらい鳴いているの?
気になる記録ですが、ゆるいルール故に20秒くらい鳴く鶏がいるんだよ!
みたいな感じになってます(汗)
声を絞り出して鳴き終わる鶏、途中でブツッと鳴き終わる鶏、いろいろな鳴き声に聴いていて飽きないです(笑)
ちなみに、土佐のオナガドリ(尾長鳥、尾長鶏)尾っぽが長い鶏のことですが、
こちらは1974年13mという記録が残っています。計測しやすいですね。
現存する鳥類の中で、一番長い尾っぽを持つと言われています。
昭和27年に特別天然記念物に指定されました!
まとめ
日本三大長鳴鶏はいかがでしたか?鶏って、こんなに鳴くんだとか、こんな鳴き方をするんだ!と驚かれた方もいるのではないでしょうか。
毎年、新潟の彌彦神社で行われている、長鳴鶏の鳴き合わせは、実際に見たほうが迫力がありそうですね。



コメント